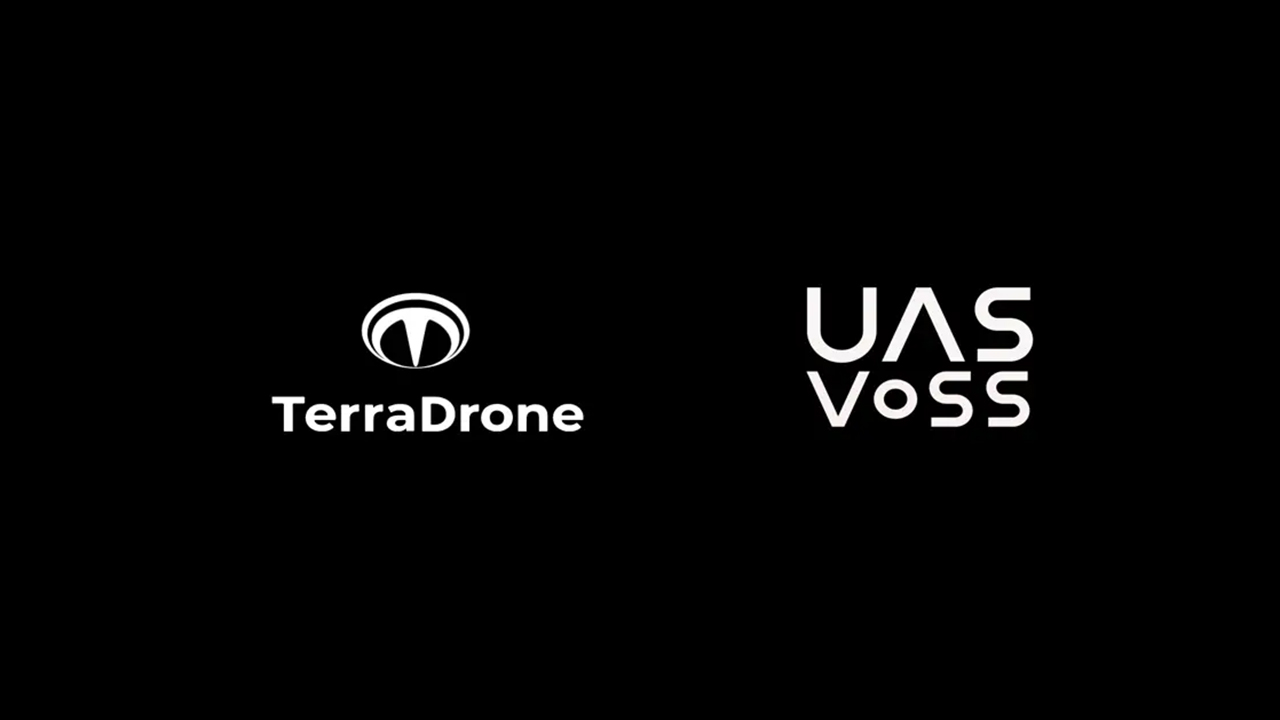高度を保ちながら、野生生物の群れ全体をカメラに捉えることのできるドローンは、いまや野生動物の研究や保全活動には欠かせない存在になっている。人が近づけば逃げてしまうような動物でも、空からなら自然な行動を観察できる──その期待を背負って、世界中の保護区や国立公園でドローン調査が広がってきた。
しかしこの便利な道具には、大きな弱点がある。少しでも良い映像を撮ろうと距離を詰めすぎると、群れの何頭かが突然、頭を上げてドローンの方をじっと見つめ始める。やがて周りの個体も次々に反応し、緊張が伝染するように広がっていく。そしてある瞬間、見ている側にはほとんど前触れなく、群れ全体が一斉に走り出してしまう。調査はそこで中断。得られた映像は「驚いて逃げるシーン」だらけになり、動物には無用なストレスだけを与えてしまうことになる。
この「観察対象の動物たちを驚かせてしまうリスク」は、動物福祉の問題であると同時に、研究の質を左右する実務的な問題だ。動物が逃走反応を示してしまうと、しばらくの間は自然な採食や社会行動が見られなくなり、行動データとして価値のある映像が激減するためである。実際、従来の人手による操縦だけに頼った調査ミッションでは、1回のフライトあたり平均14秒ほどが「逃走行動中」の映像になっており、自然な行動観察に使えるフレームは全体の約72%にとどまっていたと報告されている。
では「もっと慎重に飛ばせばいい」「操縦者をよく訓練すればいい」のかというと、話はそう簡単ではない。ドローンを飛ばす人間は、同時にいくつもの仕事をこなさなければならないからだ。風や地形、電線などの障害物を避けながら、安全にドローンを操縦すると同時に、研究対象である群れをフレームアウトさせないよう、画角と距離を微調整し続けると同時に、画面の中の一頭一頭が「落ち着いて草を食べているのか」「少し緊張して周りをうかがい始めているのか」「今にも走り出しそうなのか」を見分けることは極めて難しい。
しかしオハイオ州立大学のコンピューターサイエンス研究者らが、野生動物の集団行動を長年研究してきた生態学者たちと協力し、この課題をAIで解決する技術を開発。論文として発表している。彼らが開発したのは、「エッジ・ネイティブ行動適応型ドローンシステム」と呼ばれる仕組みだ。
AIで動物の群れの「警戒度」を可視化する
このシステムの基本アイデアは、きわめて直感的である。ドローンから送られてくる映像をAIがリアルタイムで分析し、画面に映っている一頭一頭の行動を「草を食べている」「立ち止まっている」「周囲を見回している」「走っている」といったカテゴリーに自動的に分類。そして、「周囲を見回している」「警戒姿勢で立っている」と判断された個体の割合を集計し、群れ全体の「警戒スコア」として数値化するのである。
![群れの『警戒度』を見える化――野生生物ドローン調査を変えるAI[小林啓倫のドローン最前線] Vol.97](https://drone.jp/wp-content/uploads/260105_kobayashi_ZhZNIL1T.jpg)
操縦者向けのダッシュボードには、この「警戒スコア」が分かりやすい形で表示される。スコアが低いあいだは緑色で「平常」を示し、警戒個体の割合が増えてくると黄色に変わる。さらに、事前に設定した閾値に近づいた時点で赤色になり、音付きのアラートが鳴る。どこからを危険水準とみなすか、その境目(Threshold)の設定は研究者側で調整できるようになっている。種や環境によって「驚きやすさ」は異なるため、現場の知見を反映できる柔軟性を持たせた形だ。
ここで重要なのは、このシステムがドローンを自動操縦するわけではないという点である。操縦桿を握るのはあくまで人間であり、AIは「群れから目を離さずに警戒状態をモニタリングし続ける相棒」として振る舞う。アラートを無視してミッションを続行することも、すぐに速度を落として距離を取ることも、最終的な判断は人間に委ねられている。人間の判断力とAIの観察力を組み合わせる、協働型の設計と言えるだろう。
このシステムはどれほど役に立つのか。論文では、既存の野生動物ドローン映像データセットから、シマウマやキリン、野生馬などを対象とした7つのミッションを選び出し、その録画映像に対して後からこのシステムを適用する形で評価している。そのうち4つのミッションでは、実際に群れがドローンから逃げ出す場面が含まれていた。
分析の結果、群れが逃走を開始する前に、警戒スコアが目立って上昇し始める時間帯が存在することが分かった。システムが「危険水準に近づきつつある」と判断してアラートを出せるタイミングから、実際に群れが走り始めるまでの猶予時間は、平均で約51秒。最短でも22秒、最長では91秒の余裕があった。これは人間の操縦者がアラートを見て速度を落としたり、高度を上げて距離を取ったりするには十分な時間だと考えられる。
さらに著者らは、「アラートが鳴ってから5秒以内に操縦者が回避行動を取る」という現実的な前提を置いてシミュレーションを行った。その結果、自然な行動観察に使える映像の割合は、従来の71.9%から82.8%へと約11ポイント改善し、逃走行動が映り込んでいる時間は平均14秒から1秒へと約93%も短縮されるという試算が得られた。限られたバッテリーと調査時間の中で、より多くの「意味のあるシーン」を収集できることになる。
このようなシステムが実用化され、現場に広く普及したとき、サバンナを飛ぶドローンの映像は少し違ったものになるかもしれない。そこには驚いて逃げる群れの姿ではなく、ドローンの存在にほとんど気づきもせず、淡々と日常を送る動物たちの姿が、これまで以上に長く映し出されていることだろう。